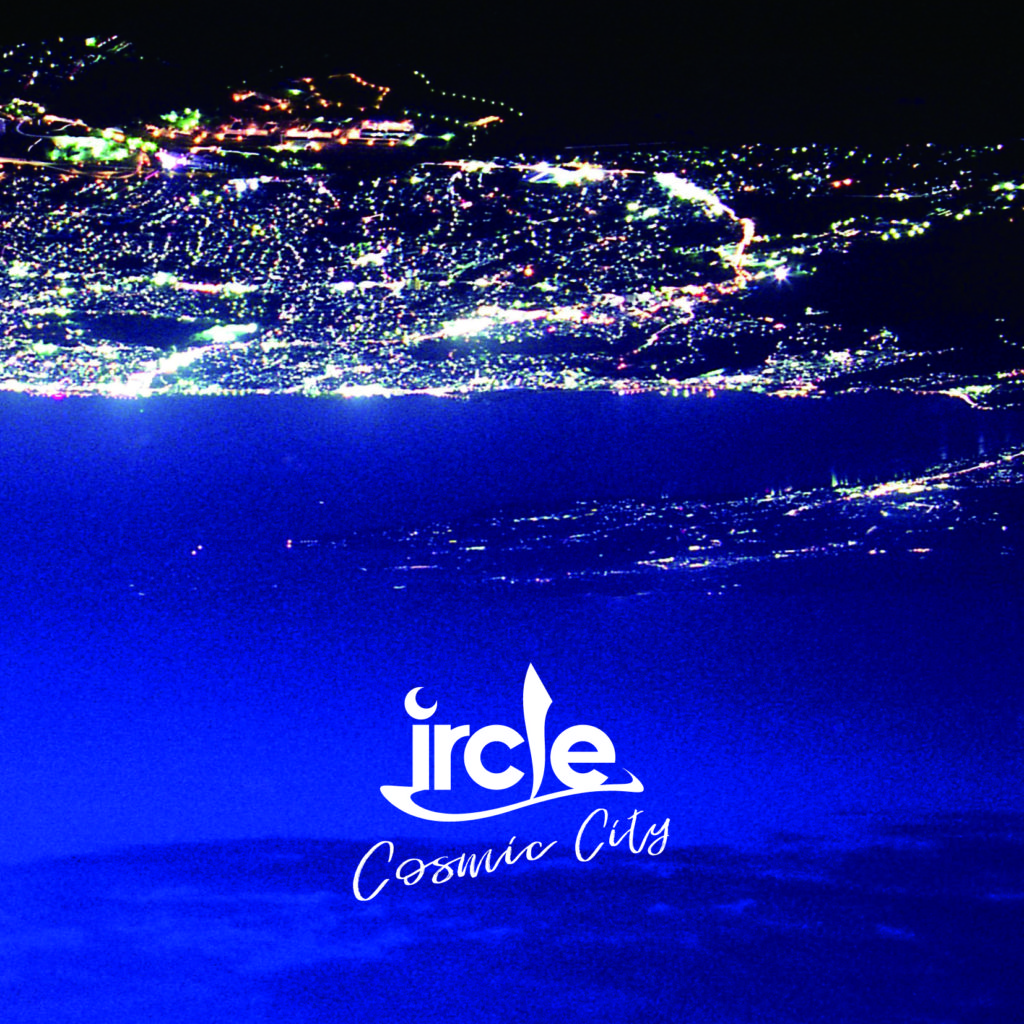Special

ircle × 矢島大地 special interview
ミニアルバム「Cosmic City」について、
矢島大地によるircleメンバー4人へのインタビューを決行。
この作品ができるまでの10,000字を超える赤裸々インタビューと
レコーディングオフショットを特設ページ限定公開!

■楽曲にもバンドアンサンブルにも、伸び伸びと4人の歌心が発揮されているミニアルバムで。歌っているのも、出会いと別れを繰り返す中で目の前の人をどれだけ愛することができるかという視点が貫かれていて、バンドとして鳴らしたいこと・歌いたいことの軸がはっきりと見える作品だと感じました。
河内健悟(Vo&G):嬉しいですね。特に何をテーマにして狙ったということもないんやけど――意図しないところでいろいろなものが繋がってびっくりした作品ですね。これまで俺達が話してきたことだったり、4人のテンション感だったりが凝縮されて、「今これでしょ!」っていうのがはっきりとしている作品な気はする。
■いろいろなものが繋がったというのは、どういう歩みが線になった感覚なんですか。
河内:この作品を作るに至るまで、人間として経験した別れや出会いが濃いものだったんですよね。そういうものが音楽にギュッと入った実感がある。
■それは、前作の『CLASSIC』から今作に至るまでの話なのか、ircleというバンドの歩みとしての話なのか、どういう意味合いなんですかね?
河内:後者の意味合いが強いと思う。バンドとして、人間としての道のりがぎゅっと凝縮できて。この4人で長い年月を過ごしてくるとさ、同じ人物と4人で接することが多いし、いろんな出会いや別れを一緒に経験してきたわけです。そういう、4人の周りで起こる人の動きが俺達の心に通って、音楽にそのまま繋がり始めた気がしたんだよね。こう……各々に近しいところでの別れを経験することで、大事にしたいものや歌いたいことは何かがはっきりしたところがあったかな。
ショウダケイト(Dr):そうだね。健くん(河内)が言ったように、何かを狙ったところは一切ない作品なんですよ。でも、近い時期に各々が大きな別れを経験することが多くて。その結果として、別れの歌が河内からも良(仲道)からも湧き出てきて。その曲達ができ上がっていく中で、それぞれの「別れ」をircleなりに意味のある歌にして、意味のある作品にしないといけないっていう気持ちが強まっていったところがある。その「別れ」っていうのが、結果的にアルバムのコンセプトっぽい部分になったのかも。

■近い時期にそれぞれ大きな別れを経験して、その経験によって、これまでのバンドとしての出会いと別れ、周囲の人への気持ちを大事に音楽で包めたっていう話ですよね。差し支えなければ、それぞれにとっての別れがどういうものだったのかを教えてもらえますか。
ショウダ:家族だったり、恋人だったり、共通のバンドの仲間が亡くなったり――そういうことが続いてしまって、必然的に、今じゃないと作れないアルバムになったのかな。
河内:そうやな。で、未だに「別れ」っていうものがどんなエネルギーになるのかわからないからこそ、その道筋をなるべく前向きなものにしたくて音楽にしたというか。たとえばさ、俺達もいつか死ぬし、だけどその先も世界は動くわけだよね。それでも、いつか終わることに絶望しているだけじゃ死ねないし、いつか終わるとしても生きていく上で大きな希望があるって信じられる歌を作りたかった。怖い、悲しい、って言ってるだけじゃ何も始まらないって改めて思えるような……そういう気持ちを注ぎ込んだ作品って、歳を重ねていく上で必要なものなんじゃないかって自分で思えたしさ。そういう意味でも、これから俺達が進んでいくための作品を作れたような気がする。
■別れそのものに対して「意味がない」と思ってしまうと、ただの絶望になってしまいますよね。そこまでの物語や道筋を大事にするから進めたり前を向けたりするわけで。
河内:そう思う。出会ったことや、そこまでの道筋にも意味がある。じゃないと、人との別れよりもひどい絶望になってしまうこともあるから。別れの先に何かがあるって思わないと、人は生きていけないですからね。そういう力を、何よりも自分達自身に生み出したかったんだよね。
■何よりも自分達に対するエールを曲に込めたかったということ?
伊井宏介(B):ああ、そういうことだと思う。だからこそなのか、バンドとして「振り切れて作ろう」っていう気持ちを持って臨めた作品なんだよね。ちゃんと河内の歌を届かせるっていう基本軸は変わらないまま、枠にとらわれず、自分達の気持ちを表現するためにいろんな曲を出していこうっていう。たとえば、むちゃくちゃ叫ぶ曲があったり、むちゃくちゃしっとりなバラードがあったり。「今のヤバいね」って笑ってしまうところまでやり切ろうっていう気持ちがバンドとしてあったんだよね。
■人として積み重ねてきた道のりを全部音楽にするために、これまでにあった枠を取っ払ったっていうことですよね。
ショウダ:そうだね。きっと今までも「振り切りたい」っていう気持ちはあったんですよ。だけど4人で話す中で、「1枚フィルターを通しての振り切り方だった」って実感することがあって。
■そのフィルターって、どういうものだったんですか。
ショウダ:曲を作ってくるのは河内や良だったわけだけど――たとえば良が作ってきた曲を河内が歌う曲にする時に、どうしても「良の曲」っていうフィルターがあったし、曲を作った人と歌う人の距離、他のメンバーの距離があったんだよ。でも、誰が作った曲だとしても「誰の曲なのか」っていう大枠から外さないと、その先には行き着けないと思ったんですよ。サウンド面で言っても、曲を作ってきた人のイメージがあった上で4人が出したい音をその軸に寄せていくことはこれまでもあったの。だけど今回は、曲を作ってきた人のイメージに寄せるとかじゃなくて、その曲がこれまでのircleっぽくなくなる恐れがあったとしても、どこまでも4人がやりたいことを伝え合って、とことんいっちゃおうっていう気持ちがあったんだよね。それも逆に言えば、どこまで言ってもircleになるっていう確信的なものがあったからこそだとも言えると思うんだけど。
■その確信っていうのは、どういう部分に持てたんですか?
仲道良(G&Cho):前回の『CLASSIC』からの流れで、4人だけのアイディアだけじゃなく自分達に関わってくれる人のアイディアも取り込もうっていう気持ちが生まれていって。特に、レコーディングエンジニアの兼重(哲哉)さんがいろんなアイディアをくれたことが前作は大きかったわけだけど。で、メンバー以外の人のアイディアを生かしていった上でも、自分達らしいと思える曲を作っていけたのが、何をやってもircleになるっていう自信になっていったんだと思う。で、それを経験して今回のキーになったのは、今年で18年になるバンドのメンバーそれぞれに対して、まだ「こんな引き出しがあったのか!」って思えたことなんです。
■メンバー個々が、曲に対してさらに自由にアプローチできるようになったということですよね。
仲道:そうそう。ケイトが言ったように、俺というフィルターを噛ませた上で河内が歌っていた曲も、一度全部取っ払った上で4人の曲にできたんだよね。積み上げてきた「ircleってこうだよね」っていうところを考えずに、この曲をカッコよくするためにはどうしたらいいのか、4人が経験してきた出会いの中で伝えたい気持ちを届けるにはどうしたらいいのか、っていう発想で曲に向かっていけたんですよ。それこそ4人が経験してきた出会いと別れっていう部分で、純粋に「それでも前に進みたい」っていうところに向き合えたのが大きい気がしていて。
■ircleっていうイメージに向かうんじゃなく、曲それぞれに4人で向き合えたと。
仲道:うん、うん。そういうことなんだろうね。前までは、俺が作った曲は特に「最終地点で自分が引っ張らなくちゃ」って思ってたんだけど、その責任感や力みを俺が持たずとも、曲を4人で背負えた感じがしたのね。そこで出てくる各々の引き出しの多さを実感した時に、プレイヤーとしても人間としても、改めてお互いをリスペクトできて。
■お互いに対するリスペクトが生まれてきた時に、バンドとしてはどういう変化や進化があったと思います?
仲道:……やっぱりバンドも人間だから、全体としてテンションが下がる時も上がる時もあるじゃない? で、バンドのテンションが下がっている時に「今って、テンションが下がってるよね」っていう会話も素直にできるようになった。疑問に思っていることを逐一解決するための会話ができるようになったし、それによって、曲に対するアプローチも、今までだったらなんとなくスルーしていたところも納得する形まで突き詰められるようになった。
前までだったら、バンドのテンションにしても曲に対しても「放っておいてもまた上向くわ」っていう空気があったの。だけど、「違和感を放っておいたら下がっていく一方なんだ」って、違和感が危機感に変わった気がする。実際、それを去年の暮れくらいにバンドで話し合うことがあったの。そこから、全員の背筋が伸びたと思うんだけど。
■『CLASSIC』の時にも、改めてメンバー同士で酒を飲んで、お互いをよりよく理解する機会があったと言ってましたよね。その上で、去年の暮れにシビアな話し合いがもたれたのは、ircleをどう振り返って、これからのircleをどう展望したからなんですか。
河内:そもそもを言えば、俺が「もっとバシバシやりたい」っていう前のめりな気持ちになって、それをみんなに話したの。ircleのチームやったり、俺らを取り巻くもの全部を作品と活動とライヴと言葉と心で喜ばせたいって改めて思ってさ。だから納得できないものは納得できないって言うべきやと思ったし、納得したものをちゃんとした形で示せない人生は嫌だっていう気持ちで、かなりの覚悟をもって話し合いの会を開いて。……やっぱり俺自身も、その話し合いの前には「もうダメなのかな」っていう気持ちになっていたからさ。やる気はあんのに、話し合えなきゃ何もできないじゃんって。
■その「もうダメなのかな」は、何に対して?
河内:もちろん状況をどう膨らませるかっていうことは頭の片隅にはあるけど、そんなことよりも、ものを作るっていうこと自体にテンションが上がっていかなくちゃダメでしょ。そこに対してテンションが上がっていない空気を俺は感じてたの。でも、俺はもっとバンバン曲を作って、バンドとして動いていきたかったんだよ。でも、元々できた人間を中心に集まったバンドではないからさ。ちょっとでも話し合いを怠ったら、全部が適当になってしまう4人なんですよ。だから、ちゃんと逐一言い合えないといけないよねって。そんなの当たり前のことやけど……でも、本当にそういうバイオリズムをちゃんと感じとらないとダメなんですよ。
■そういう話が河内くんから出てきた時に、どういうことを思ったんですか。
ショウダ:改めて健くんが「やりたいことはやりたいって言おう」、「ダメなことはダメって言おう」って話してくれた時に、バンドに対して個々が責任を負う必要があるんだって改めて実感できた。それこそ4人の空気の読み合いというか、バンドのテンションのバイオリズムがあったなって気づいて――でも、言葉にせずとも「河内は次にこうくるだろうな」とか、「良がこうしたら、こうなるだろうな」とか、勝手に解釈して話を進めているだけじゃ、どこにも責任がないんだよね。だけどやっぱり、お客さん以前にチームに対してすら自分達の意志をハッキリ伝えられてなかったんだなって思って。そういう曖昧な空気を作ったことに対して悪いと思ったし、河内が「もっとircleは面白くなる」って言った時に、まだまだやれるんだなって思えて。
■特にircleの場合、ほぼ幼馴染に近い関係から始まってるバンドじゃないですか。バラバラなものを通過してきた人が集まったバンドではなくて同じ青春の中で育ってきた4人だからこそ、言葉にしないでも大丈夫っていう空気は強かったのかもしれないですよね。で、その青春のまま突き進めることも凄く素敵だけど、青春だけでいいと言える季節とお別れすることで、今こそ次のステップを踏もうとしたとも言えますか。
河内:ああー、そういうことかもしれん。思い出してみると、昔コピーバンドをやってた中学生の頃も、会話なく淡々とやってたのよ。だからこそ、お互いにテンションが下がるモードも知ってるの。4時間くらいスタジオに入ってれば何か生まれるっしょ、みたいな感じでいた時間も長かったからさ。でも………もう、めんどくせえ!
■え、何が!?(笑)。
河内:いや、モヤモヤしたままいるのもめんどくせえし、曖昧なまんまもめんどくせえ(笑)。明日の朝みんなに言えるかな?って考えながら寝るのもめんどくせえし、それじゃ楽しくないじゃん。だって、楽しいからバンドをやりたいと思ったのに。だったら、言え!って感じやし、やれ!って話じゃん。楽しくやらなきゃ間違いなく音に出ちゃうし、バンドが楽しいって思えなきゃ何も伝わらんのよ。だから、各々が素直に自分を表現して、バンドが楽しいと思えるところに向かいたかったの。

■感覚的な言い方ですけど、眠る前のモヤモヤが曲と歌になるタイプだった河内くん自身が大きく変化しましたよね。
河内:確かにそうやな(笑)。でもまあ……みんなが言いたいことを言えない空気を作ったのも、俺が悪いんだろうね。俺がどんどん萎縮していったし、「これは言うべき」とか「これはいうべきじゃない」とか考え込んで、ひとりでモヤモヤしてた。それがヴォーカルとしてダメなところだったし、だからこそ俺が話し合いの会を開かなくちゃいけなかったんだよね。
仲道:元々、幼馴染として集まったバンドだって言ってくれたよね。だからこそ言葉にできていなかった部分……何よりも、「みんな音楽が好きなんだな」って思えたのが凄く嬉しかったんだよね。それこそ「今、こんなのを聴いてるんだよ」って話すのが今さら楽しかったりさ(笑)。だけど、自分ひとりだけで聴いてた音楽を話し合うだけでも、これまで知らなかったお互いの引き出しを知れることがある。それがそのまま、楽しさに繋がっていった気がするね。
■メンバーのことを面白がれるようになった。
伊井:まさにそう。だから、自分のこと以上に他のメンバーに興味を持つようになってきて。そうなると、もっとこうしたほうがいいんじゃない?っていうこともハッキリ言えるんだよね。だって、自分のベストは自分自身で出せるじゃない? その上で、他のメンバーが何を出してくるのか、それで何が作れるのかっていうワクワクできるようになってきて。今まで、どれだけ自分のことだけしか考えてなかったかっていう話なんだろうな。それくらい、各々が俯瞰でバンドを見られるようになったと思うんですよ。
■俯瞰で見た時に、ircleというバンドの面白さはどこにあると思えました?
伊井:うーん……不器用なところが取り柄なのかなあ。
河内:結局は「やるしかねえぜ!」しかないからね(笑)。
伊井:そうそう(笑)。でも、昔から不器用なヒーローが俺は大好きだったから。とにかく突っ走るしかないんだけど、そこでずっこけたりするところが人間臭くてカッコよかったりするじゃないですか。そういう表現をしてきたバンドなんだなって、客観的に思えましたね。
■ircleというバンドが歌い鳴らしてきたこと自体が、不器用な人が不器用なまま負けて終わらないようにっていう願いでしたよね。
河内:ほんとにそう。どうしても上手くできなくて、生きづらいと思う人達のための歌を歌いたい。それだけは変わらんよな。そういう生きづらさや悔しさを忘れたような歌だけは作らないよ。実際に忘れてないしさ、きらびやかじゃなくていいって思う。
伊井:ircleって、アンパンマンみたいだよね。“あふれだす”っていう曲にも、<これぐらいしかないけど/全部あげる>っていう歌詞があるじゃないですか。俺にはこれぐらいしかないっていう痛みを持ちながらも、それも全部あげることであなたを幸せにするんだっていう気持ちは、全部の曲に通じてるんだなって。
■その気持ちは、別れを歌いながらも、その先の幸せと愛を願い続ける今作の歌でより一層ハッキリしていますよね。たとえば新しい王道と言える“ラストシーン”。すぐに最後の時を迎えるかもしれないからこそ今をどう生きるんだ?と自分自身に問いかけていく歌なんですが。
仲道:これは、俺が作った曲ですね。発端は、俺が恋人と別れたことなんだけど……今まで感じたことがないくらいの悲しみとか痛みを経験したんだよね。だけど、それを自分だけで堪えていても押し潰されて死んでしまうと思って。なんとかしてこの気持ちを外に出さなくちゃと思ったし、だとしたら、できるだけ綺麗なメロディにしなくちゃ供養できないと思ったし。その気持ちを伝えながら曲を健くんに渡したんだけど。でも、それこそ俺のフィルターは一旦外して、あくまで材料になる曲を詞を渡して、それを仕上げるのは健くんだっていう意識だったんだよね。
河内:で、それを受け取った俺は、良に向けて歌った。
■一番近くて一番大事な人へのエールソングなんだ。
河内:そう。俺も、歌ってる時はグッときてて。曲をもらった時は、「なんとなく別れの曲なんやろうな」くらいだったの。でも良自身は「書き換えてもいいよ」っていうモードになってきてたから、そこに俺の想いも入れて。
■<最後の最後の一秒に会いたい人が浮かぶか/会いにいこうぜ伝えて死のうぜ>っていうところが熱くて切実で大好きなんですよ。“本当の事”で<愛してるよって/愛すべき物全部に本気で言えたらきっと/空の色すらも変わんだよ>と歌っていたircleがここまで来たんだっていう道のりや覚悟、全部が感じられる。
河内:ああー、確かにそうやな。なんかこう……やっぱり別れの歌のまんまだったり、言いたいことを言えないままだったり、それだけの曲にはしたくなかったんだよね。じゃあどうするんだよって、俺ら自身に歌いたかった。それこそ良に向けて歌ったっていうことがそうだけど、歌いたい人に向けて歌いたいと思ったんだよ。だから、パキッと方向の定まった歌になったと思うし。
■そうですよね。実際、“ラストシーン”はお別れの歌にはなっていないじゃないですか。別れがあるからこそ、今この一瞬をどれだけ大事にできるのか。お別れしたけど本気で愛していたのは本当のことだし、だったら何かをまた愛せるじゃないかという希望。そういうエネルギーに転化できているのが、この曲とこの作品の突き抜け感に直結してるんだろうなって。
伊井:うん、うん。これがお別れの歌のままだったら、これだけ前向きで前のめりな楽曲にならなかっただろうし。どうしても前向きな歌にしたいっていう気持ちがバンド全体の意志になってるんだと思う。

■そして“ねえダーリン”は、これまでにないトラッドパンクになっていて。今おっしゃった前のめり感と音楽的な新機軸が両方感じられて面白いです。
河内:これは俺の作曲ですね。ただただ、何も考えずに作っていった(笑)。
ショウダ:(笑)そういう曲に、ギターとベースが決定打を打った感じはしますね。曲の方向性がそこで決まったというか。
伊井:河内が曲を持ってきた時点で、なんとなくカントリーっぽいなと思ったんですよ。それで、ネットでカントリーのベースフレーズを検索して、練習してフレーズを作って。今までは、全部自分から出てきたものじゃないとダメだっていう意識があったんですよ。でも今回は、自分のエゴというよりも曲に対して一番いいものを入れることしか考えてなかった。……今話してても思ったけど、ほんとに自分よりも曲のことしか考えてなかったね(笑)。
ショウダ:“ねえダーリン”のドラムも、健くんが「こういうふうに叩いて!」って言ってきてさ。で、それってバンドでオリジナルの曲を作り始めた頃に近くて、そこからだんだん、「ドラマーは俺なんだから、ドラムフレーズは俺から出てくるんだよ」って感じになっていったんだけど。でも、それ以上に曲がどうかっていうことのほうが大事だったんだよね。
仲道:で、俺はその上で伸び伸びとやらせてもらってます(笑)。
■はははは。ircleの伝家の宝刀である激烈主張ギターが炸裂してますよね。で、ここでも<気づいていつか止まる/時間に気づいてねえダーリン>と歌っていて。女性視点で報われない恋を歌っている曲ですけど、どの歌も、終わりを起点にしてここからを繋いでいこうとする意志が一貫してる。
河内:最初の話に戻っちゃうかもしれないけど、やっぱり、望まない別れが異様に多い1年を過ごしてきたのが大きいよね。死んだらどこに行くんやろ?とか、酒を飲んでる時ですら思わんようなことを考えざるを得なかったからさ。友達が急に死んだりとかさ。青春とはまったく違う、大人としての多感な時期になってきましたよね。こう……大人になっていくこと、持ち時間が減っていくことを受け入れている感じがする。
■大人になるとは、別れや喪失や痛みに慣れていくことだっていう発想もあるじゃないですか。でも実際のところ、失うことや別れにおける痛みや悲しみは強烈になっていくんじゃないかと思っていて。それは、大事なものが増えてるっていう意味でもあるわけですよね。で、ircleはそういう意味で失いたくない愛や絆をここで歌にしていると思うんですよ。
河内:……やっぱりさ、子供の頃って何も考えず勝手に話してたじゃん。それでもたとえば友達が死んだら悲しいは悲しいけど、ふわっとした悲しみだったと思うの。でも大人になってみたら、自分の気持ちと人の気持ちをどう通わせたらいいかを考えるようになるでしょ。俺に対してどういう思いやりを持ってこうしてくれたんだとか、その人の人生の背景まで考えながら心を通わせたいと思うようになる。だから、その人がいなくなることや、死んでしまうことへの痛みが増えていくんやと思う。それを、何より自分達自身が前を向いて認めていく歌が必要だったんだろうね。
仲道:どんな種類の悲しみだって、悲しいことは悲しいじゃない? でも「そんな小さなことでクヨクヨするなよ」って言われたとしても、やっぱり人それぞれにどうしても悲しいことがあるし、その一つひとつに向き合うしかないんだっていうことを認めていくのが、大人になるっていうことなんだと思った。
■だから今回の歌って、これまでよりもさらに狭くて小さい日々の歌になっていると思ったんです。自分の目の前の世界だけしか歌っていないし、それをどう信じてどう愛するのかっていうことしか歌っていない。
仲道:確かにそうだよね。それこそ『Cosmic City』っていうタイトルにも表れてるけどさ、「宇宙の町」っていうのは――小さい町なんだけど大きな宇宙であるっていうことを表現してきたのがircleだと改めて感じたのね。小さな範囲で生きている人間も、大きな宇宙も、全然別のものじゃない。それこそ健くんも、今回はやたら「宇宙」っていう言葉を連発しててさ。掛け替えのない人の存在を意識すればするほど、大事な人が増えれば増えるほど、それぞれの人に別々の宇宙が存在してるんだっていう気持ちが強烈にあったんだよね。
■河内くんは、どういう気持ちで「宇宙」を捉えてるんですか。
河内:まあ、俺は小さい頃から宇宙の話が大好きでさ。爪の垢の中にだって宇宙が存在してるんだ、みたいな想像が好きだったんだよね。そしたらどんなに大きな悲しみも小さく思えるし、どんなに小さな悲しみも大きく思えるじゃん。だから逆に言えば、俺達から見た大きな宇宙の悲しみだって、俺らに伝わってくるんだよ。そうやって想像していたことを、今回の作品で自分が納得する形で説明したかったというか……ガキの頃から考えていることと歌っていることの歯車が合ったような感覚があったんだよね。
■それは、人生には終わりと別れが必ずくることを強烈に意識したから人間一人ひとりの生活を掛け替えのないものだと思えて、それぞれが無限の宇宙を持っているという意識が強くなったということ?
河内:うん。きっと、それはずっと持っていた意識なんやろうけど……たとえば、街でギャーギャー騒いでいた人でも家に帰ったら寂しい気持ちで膝を抱えるとかさ。そういう一人ひとりの生活を想像するのは楽しいことで。そうやって想像すると、人それぞれが各々の人生を生きているっていうことが自分にとっても救いになったり、宇宙の中で繋がっていると思えるんだよ。全然バラバラな人間だったとしても、それぞれが自分の生活を大事に生きてるっていう意味では近いわけで。
■それをハッキリと歌われているのが、ラスト2曲である“アンドロメダの涙”と“ペルセウスの涙”だと思いました。特に“ペルセウスの涙”においてはポエトリーというか叫びだけが貫かれていて。<ばあちゃんも母ちゃんも恋人も音楽も街も/消えてもいつか穏やかな共通言語で交わるって/信じてもいいやろ>という言葉に集約されていくというか。
河内:みんながバラバラなことなんて、もうわかり切ってるじゃないですか。それに、わかり合えないことがあるっていうこともわかってる。だからこそ、最後の最後で無になった瞬間に<穏やかな共通言語で交わる>って思わないとやってられない。そうあってくれないと、すべてのことが収まらないんだよ。そういう気持ちでいないと、生きてるうちに起こることが何もかも悲しいとしか思えない。で、悲しいことしかないわけじゃないって言い切るためには、一番最後で必ず交われるって歌うしかなかったの。で、それが俺の考えていた宇宙そのものだったんだよね。歌いたかったことが歌えた実感があるし、その全部を、4人で背負えたから。そういう意味で、バンドとして新しいステップに行けた実感がありますね。
仲道:人と一緒で、きっと自分達の真ん中とは何かを探し続けていくんだろうけど。でも一方では、歪なままでもいいんじゃないかなって思うし、歪なものでも、何かが爆発したり溢れ出したりする瞬間を綺麗なものだと思ってもらえたらいい。そうやって、どこまでも突っ走るバンドでありたいなと思う。
河内:照らすっていう意味じゃなくても、頭が悪くても、太陽みたいでありたいよね。なんで燃えてるかわからないけど、燃え続けてるっていうさ。そのために大事な、自分が燃えられる理由――大事な人の存在とか、優しくしたいと思えるものとか。それに改めて気づけたから。燃え続けるよ。
■その意志が貫かれている作品だし、本当に素晴らしいです。名作おめでとうございます。
河内:ありがとう。これからもよろしく!
インタビュー / 文=矢島大地